3月23日(土)13:00~16:00の日程で「総合学科5世代交流会 with 同友会」が開催されました。今回は、三木高校総合学科が5年前から香川県中小企業家同友会(以下、同友会。)にご協力いただき実施している「インタビューシップ」を経験した24期生~28期生の5世代の在校生、卒業生と同友会所属企業の方が一堂に会し、交流するという試みを行いました。今回も企画・運営すべてを在校生と卒業生で作る」実行委員で行いました。当日の様子はNHKの夕方のニュースでも紹介されました。


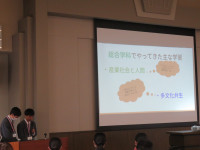
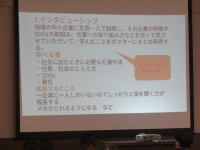


当日の日程は以下のとおりです。
12:30 受付開始
13:00 開会式(校長挨拶)
13:10 各学年報告会(24期生~28期生代表者プレゼン)
13:50 報告会終了
13:55 班別交流会開始
「インタビューシップについて」
インタビューシップ前後で変化したこと
インタビューシップを行う利点
インタビューシップをもっとパワーアップするためには
14:15 「三木高校について」
三木高校の良さとは
三木高校に入る前のイメージと今
三木高校に来て成長したこと
三木高校で学んだことどんな場面で活かすことが出来たか
14:35 「将来について」「フリートーク」
これから挑戦したいこと
どんな人になりたいか
将来のために今頑張っていること・頑張りたいこと
14:55 交流会終了
15:00 班別交流会の内容共有
15:20 同友会代表挨拶
山形大学松坂教授挨拶
15:55 閉会式(生徒代表挨拶)
写真撮影






<班別交流会での意見>
①「インタビューシップについて」
・縦のつながりを深くする
・次の世代に引き継ぎをする→体験談等を通して
・インタビュージップを2年生でも行う(自分の興味や進路に関わる事業所へ)
・勝手な思い込みをなくす
・視野を広げる
・自分に自信がついた
・企業を見て、大企業以外には入らないという自分の謎のプライドがなくなった
・企業の方も学生から学ぶことがある
・話し合いの場(企業との)をインタビューシップ前に取り入れる
・企業さんが社員に対するケアをよく考えている
・自分の意見を持つことは大事




②「三木高校について」
・自分の興味があることを自分で考えられる
・総合学科に入ってよかった!
・少人数制→生徒と先生の距離が近い
・先生が良い→距離が近い・優しい
・コミュニケーション能力UP
・自分を中心とした世界を考えられる
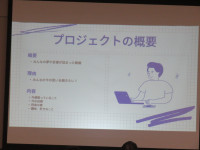
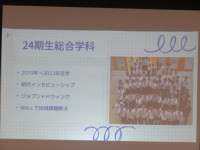


③「将来について」「フリートーク」
・人に感謝できる人になりたい
・責任を持てる人になりたい
・夢を後押ししてくれる大人の方がいた
・企業→地域活性化・学生の成長を見たい
・総合学科これからも安泰
・将来の夢=やりたいこと
・このような話し合いの場は月一にするべき
(興味のある職業とは違っていてもいろいろなところからの視点を取り入れられるから)
・大人の人同士でも結果が同じになるがそこまでの過程が違った
・質問を返すだけではなくそれに対する価値観も教えてくれた
・他人のため、相手のためを思って考えられるのが大人




<「総合学科5世代交流会 with 同友会」の感想>
<24期生>
・まとめた形になるけど、今の高校生と関わることができてよかった。
・一生懸命に場を回そうとする高校生の姿に感心した
・また参加したい
・もう一度開催するなら、県外に進学している友達が帰省夏休み(8月〜9月ごろ)か春休み(2月〜3月)の年2回開催もいいんじゃないか(大学生のみの都合)参考までに!




<25期生>
・いろいろな世代と交流出来て良かった。色んな考え方生き方が知れてためになったと言ってました!
<26期生>
・今日は素敵な機会をありがとう😭💖準備大変やったと思うけどお疲れ様!人と話せて良かった。また機会があったら参加させて〜!
・企業さんがこの前も同じ班やったよねって覚えてくれてて嬉しかった💞
・学年一つしか違わんのにレベルアップしていて驚き桃の木!○○さんと私らやってないよね怒?!笑って話したよん。あんなに大人の話を聞けて、自分の事を大人に話す機会ないから何回もやるべきだぜ!ていうか、またやりたい~!
・今日は誘ってくれてありがとう! めっちゃ楽しかった。またやりたいって思った!






<27期生>
・インタビューシップの前後の変化について、受け入れる側である企業さんの話も聞くことができて、興味深かった。インタビューシップは生徒と企業さんの両方にとって、得られるものがあるのだと思いました。改めて素晴らしい企画だと思った。
・将来について、大人の方々の意見を聞き、不安が少しなくなった気がする。肯定的な意見や新しい発想を得られて、より自分に自信を持てたり、視野が広がったりしたように感じた。
・これからも開催すべきだと思ったし、もっと多くの生徒に参加して欲しいとも思った。
・同友会さんの方や他校の生徒、先生方との交流が多かったが、今回の交流会では同友会の方、生徒だけでなく、卒業生も参加してくれたことで、知らなかったインタビューシップや高校の軌跡を知ることができてよかった。
・未成年の価値観と大人の方の価値観の違いが交流会の中でよくわかった。未成年の中でもやっぱり大学生の価値観は自分たちより社会に接している分、大人に近かったり、一貫性があったりして、すごいなと思った。
・学びが多く凄く良い会だった。班のメンバーが変われば感じることも考えることも変わると思った。
・企業さんに、「三木高校から色々な高校にインタビューシップの取り組みが広がっているんだよ!それに三木高校の生徒さんの発表は他の高校と違って、会社の概要だけではなく自分の体験したことや成長したことを発表しているからすごくいい!!」と言っていただいて嬉しかったです。また、先輩や後輩と三木高校の良さやあるあるを共有できて、やっぱり三木高校に入ってよかったな〜と感じました! とても楽しかったです!参加してよかったです!
・進路に合わせてグループ分けしてくれたおかげで、入試のことも先輩に質問できました!ありがとうございます🙇
・今までも同友会さんと話す機会はあったけど、改めて近い距離で、今までに聞けてなかったことまで聞けたと思う。そして、今回は先輩たちも参加していたので、インタビューシップ初年度の先輩方はどんな反応だったのかとか、先輩たちがインタビューシップを行った時はどんな感じで運営していたのかなど、自分たちが見た事もないところを聞くことが出来て、視野が広がったと思う。






・みんなで自分の将来の事を語り合った時に、自分のこともはっきり考えたし、後輩の気持ちの強さに圧倒された。先輩たちはやっぱり自分たちより大人な考えを持っているなと感じざるを得なかった機会だった。すごく楽しかったです!
・色んな立場の方の考えや将来の夢について知ることができて面白かったし、良い経験になったと思います。また、インタビューシップについて企業の方の考えや悩んだことについても知ることができたので良かったです。
・将来や進学のことで今高校生の私がやるべきことについて色んなアドバイスをいただいたのでとてもためになりました。自分の考えを他人に話すことで自信になったし、いろんな方としゃべれて楽しかったです。
・三木高校の総合学科に入って良かったと改めて感じました。また参加したいです。
・同友会の方々も来ていたので、インタビューシップのことについて一番長く話しました! 三木高生もインタビューシップに向けて学校でいろんなことを準備して企業さんへ訪問していたけど、企業さんも私たちのためにいろんな工夫をしてくださっていたことを改めて実感することができました。
・印象に残っているのが、私たちが質問をして、企業さんが答えるということが多いと思うけど、逆に私たちに質問をするという方法もあるということをおっしゃっていました。






・将来についても話しました!同じ進路に関係している人達が集まっていたので、アドバイスをもらいながら話し合いが進んでいったのでとてもよかったです!
・もっと進路に関することを聞いておけばよかったなと思いました🥹
・私の班ではインタビューシップについて一番長く話しました。中学のときの職場体験と何が違うのか、インタビューシップ、成果発表会においてのSDGsの観点は本当に意味はあるのか、インタビューシップを通して地元へ残りたいと思ったのか、もしくは思えるのか、などなど自分の意見を班員間での質問を交えながら共有することができました。このような、普段関わることのない違う世代の方、企業の方と話すことは自分の考えを確立する場でもあり、考え方を広げる場でもあるので是非とも今後とも続けてほしいし、参加したいと思います。
・インタビューシップについて、同友会の方が「社員の教育にもなるし、むしろ社員が三木高に来てもいいんじゃないか」と言っていて、企業側から見ても利益が大きいと知ることができました。
・また、自分のやりたかったことが人に話したことによってまとまったし、それについてアドバイスや情報を貰う事が出来ました。
・同友会の方々の相手から話を引き出す上手さを体験することが出来て、大人になるというのはこういう事なのだと実感しました。インタビューシップも含め、普段関わらない方と話せる機会は良い経験になると思います。もっと多くの人に参加して欲しいと思いました。
・とても楽しかったです。次があればまた参加したいです。






<28期生>
・色々な世代と交流出来て新しい考え方が生まれ、視野が広がった。
・同友会の人が仕切ってくれなくてもできるようになりたい。
・普段関わりのない、でも同じインタビューシップを経験している人たちと話をすることでより学びが深まった。そして会話が弾みやすくとてもいい時間を過ごせた。
・色々な世代の人のインタビューシップでの経験を知ることができ、良い交流会だったと思う。また、将来の夢についても深めることができた。
・5世代の大きな縦のつながりを作ることができた。この縦の繋がりを活かして進路探究を進めたい。
・世代ごとに体験したことや考えること、今何をしているかが違っているので、異なる境遇にある人の意見を聞くことで、今の自分では到底思いつかない考え方を教わった。学んだことを活かして新1年生に伝え、これからの生活に取り入れようと考えた。
・世代によってインタビューシップで具体的に行った内容が違っていて、話を聞いていて新鮮味があり面白かったです。企業の方にも、年々より深いものになっていると言っていただけたので嬉しく思うと同時に来年の一年生にさらに良い経験をしてもらえるようにサポートする役割を果たしたいと思いました。






・インタビューシップはコロナでできなかった世代もあったし、今の1年生は進路探究のことについて、あまり詳しく分かっていなかったため、今度5世代で集まれる機会があったら進路探究や個人探究についてよく話し合いたい。
・率直に楽しかったです。大人の方だけではなくて、同じことを経験している先輩の方とも話すことができてとてもよかったです。また交流会ができたらいいなと思います。次回は自分の進路に合った人や興味のあることの人と交流ができたらいいなと思います。
・5世代と同友会さんという幅広い年代の方たちとお話をして、それぞれの経験や思いを聞くことができてよかった。経験が世代によって違うからこそ、同学年だけではできないような、世代ごとの経験を繋げながらの話し合いができたと思う。
・現時点で考えている自分の進路について説明し、質問にも答えることでより一層努力しなければいけないと改めて感じることができた。






・全員の前で話すのが初めてで緊張した。
・自分の意見を頭の中で順序を考えながら話せるようにしたいと思った。
・色々な人と話すことが出来て自分の考えを深めるとてもいい機会となった。ちゃんと話せるか不安だったけど、同じ班の人達が親しくしてくれたので自分の意見を言いやすかった。
・自分の思っていることを頭で考えながら伝えることが出来て良かった。それぞれの世代での問題や失敗を聞くことができて、すごく勉強になった。






<総合学科の取組へ戻る>